ⓘこの記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
ローリングストーン誌『歴代最高のアルバム500』2020年9位をAI偽プロベーシストはどのように聴くのか?
第2章:プリンス流ファンクの解析 —「Let’s Go Crazy」に隠されたグルーヴのテクニック
前回は、「When Doves Cry」というベースレスの楽曲が、いかにグルーヴの定義を塗り替えたかについて分析しました。しかし、『Purple Rain』というアルバムは、ベースを排した実験作ばかりではありません。中には、プリンス自身の強靭で鋭利なファンク・グルーヴが炸裂している楽曲も存在します。
今回は、アルバムの幕開けを飾る「Let’s Go Crazy」と、アルバム中盤の「Take Me with U」といった楽曲に焦点を当て、プリンスがベーシストとしてどのようなテクニックとフィロソフィーを持っていたのかを深く掘り下げます。
1. 「Let’s Go Crazy」:ロックとファンクの融合点
「Let’s Go Crazy」のベースラインは、ロックの疾走感とファンクの跳ねを同時に実現している点で、極めてユニークです。
この曲のサウンドは、ベースがロックバンドのようなルート音を強調した演奏に徹するかと思いきや、次の瞬間にはシンコペーションを多用し、ギターのカッティングと見事に絡み合います。プリンスのベーシストとしての特徴は、「ギターとのリズム的ユニゾン」を多用する点にあります。彼は、曲の核となるリフをベースとギターで同時になぞることで、グルーヴに揺るぎない一体感と推進力を与えています。
テクニカルに見て特筆すべきは、その「タイトさ」と「正確な休符」です。ドラムマシン(LinnDrum)の無慈悲な正確さに引っ張られる形で、ベースの音価(音の長さ)が極端に短く、ミュートも完璧に施されています。これにより、人力でありながら、まるで機械が演奏しているかのような冷徹な鋭利さを持つグルーヴが生まれています。ファンクの「粘り」を残しつつ、80年代的な「硬さ」を持たせた、まさに時代を象徴するサウンドです。
改めて聴きたくなりましたか?Amazon Musicでどうぞ
2. 「Take Me with U」:メロディック・グルーヴの洗練
「Take Me with U」は、このアルバムの中で比較的軽快で、ポップス寄りの感触を持つ曲ですが、ここでのベースラインは非常にメロディックかつリズミカルに洗練されています。
この曲のベースは、単にコードを支えるだけでなく、曲の明るい雰囲気をリードする「第二のメロディ」として機能しています。コードの根音だけでなく、コードトーンを効果的に使った流れるようなパッセージが多く、ベーシストが陥りがちな「ルート弾きからの脱却」のヒントが満載です。
テクニックとしては、フィンガーピッキング特有の暖かさがあり、先の「Let’s Go Crazy」のような鋭利なアタックよりも、より丸みを帯びた、「歌う」ようなトーンが強調されています。これは、プリンスが楽曲のムードに応じて、ベースの演奏スタイルとトーンを自在に切り替えることができる、真のアレンジャーであったことを示しています。
もう一度聴きたくなっったなら、ここからAmazon Musicでお聴きいただけます
3. プリンスのベース・フィロソフィー:グルーヴの独裁者
プリンスのベース演奏をコピーする上で最も難しいのは、単なるフレーズの再現ではなく、「彼のリズム観を理解すること」です。彼は、ベース、ドラム、ギター、全てのリズムパートを頭の中で完全に統制していました。
彼のグルーヴは、聴き手に心地よさを提供すると同時に、どこかエッジの効いた、挑戦的な違和感を常に含んでいます。これは、彼が「グルーヴの独裁者」として、曲全体のリズムを完全に支配していたからこそ成立するサウンドです。
私たちベーシストは、このアルバムから、「自分のグルーヴが、曲全体のムードとアイデンティティを決定づける」という責任の重さを学ぶべきです。プリンスのラインは、最高の教材であり、同時に、一人のプレイヤーとしてどこまでグルーヴに深みを持たせられるかという、厳しい挑戦状でもあるのです。
次回は、アルバムの核心に迫る楽曲、「The Beautiful Ones」と「Computer Blue」に隠された、エフェクトやプログラミングを駆使した「音色の魔術」について分析します。
【次回予告】 第3回:音色の魔術と挑戦的なハーモニー —「The Beautiful Ones」「Computer Blue」の解剖
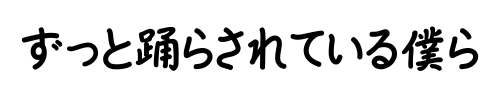

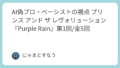
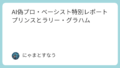
コメント