ⓘこの記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
ローリングストーン誌『歴代最高のアルバム500』2020年3位をAI偽プロ・ベーシストはどのように聴くのか?
ジョニ・ミッチェル『Blue』— 孤高からジャズとの融合へ
1. 究極の「引き算の美学」としての『Blue』
プロベーシストとして『Blue』を聴く時、まず心を打たれるのは、その「ベースの不在」が持つ強烈な存在感です。世の多くの名盤が分厚いサウンドで土台を築くのに対し、本作は歌とピアノ/ギター(特異なオープンチューニング)が主軸を成します。これは、技巧や音数を排し、感情の核を裸にする究極の引き算の美学。ベーシストが常に考える「グルーヴの提供」や「和声の補強」といった役割が、意図的に放棄されているのです。ベースレスという選択は、ジョニ自身の脆さや孤独といった個人的な告白を、最も親密で生々しい形でリスナーに伝えるための、厳しくも完璧な判断でした。
2. ベースの「登場」とフォーク・ロックの土台
全曲がベースレスではありません。「Carey」では、スティーヴン・スティルスがベースとギターで参加しています。彼の抑制されつつもリズミカルなベースラインは、この曲に唯一の活気とドライブ感をもたらし、アルバム全体のムードの中で「外の世界」や「旅の喜び」といった要素を際立たせています。しかし、ここでのベースはあくまでフォーク・ロックの枠組み。ルートとシンプルなパッセージで楽曲を支える、伝統的なベーシストの役割に留まっています。この段階ではまだ、その後のジャズ的な自由は影も形もありません。
Amazon Musicで聴いてみる?
3. 和声の探求とジャズへの萌芽
ジョニ・ミッチェルが多用するオープンチューニングは、当時のフォーク・シーンでは異例の、極めて複雑で個性的な和声を生み出しています。このコードワークは、既にジャズ的な響きを内包しており、後に彼女がジャズの巨匠たちと共演する素地となりました。不安定で美しいそのハーモニーは、安易なベースラインを許しません。もしここでジャズ的なアプローチを試みれば、楽曲の親密さが失われかねない。そのため『Blue』では、最小限の伴奏が最適解だったと言えます。彼女の音楽が、既にフォークの枠を超え、ジャズの世界へ歩みを進める準備をしていたのです。
4. ベーシストとの出会い:ジャコ・パストリアスとの革命
『Blue』での内省的なアプローチを経て、ジョニはキャリアを重ねる中でジャズの世界へ深く傾倒します。その転換点となったのが、天才ベーシスト、ジャコ・パストリアスとの出会いです。
ジャコは1970年代後半のアルバム『Hejira』や『Don Juan’s Reckless Daughter』などに参加し、ジョニの音楽に革命をもたらしました。彼のフレットレス・ベースによる歌うようなメロディアスなライン、類まれな和声的知性、そして卓越した技巧は、ジョニの複雑なコード進行と見事に融合。ベースが単なるリズム楽器ではなく、もう一つの主旋律として機能し始めます。ジャコはフォーク・ロックの土台を完全に打ち破り、ジョニの歌声と対等に渡り合うリリカルな存在として、ベーシストの役割を再定義しました。
5. 巨匠との協働:チャールズ・ミンガスとの遺作
さらにジョニは、ジャズ界の巨匠チャールズ・ミンガスと、彼の最後のアルバムとなる『Mingus』で協働するという驚くべきプロジェクトを実現します。ミンガスは彼女に楽曲を依頼し、ジョニは偉大なベーシストにしてコンポーザーの音楽を解釈し、そこに自身の歌詞とメロディを乗せました。これは、フォーク・シンガーがジャズの巨匠と創造的な対話を試みた、音楽史においても特筆すべき瞬間です。
『Blue』の孤高のフォーク・シンガーから、ジャコやミンガスという巨匠たちと渡り合うジャズ・アーティストへの変貌は、ベーシストの視点から見ても非常にドラマチックです。『Blue』の「不在のベース」から始まった旅は、やがて「革命的なベース」(ジャコ)と「巨匠のベース」(ミンガス)へと繋がり、ジョニ・ミッチェルの音楽が持つ和声的な深みと自由な精神を証明し続けているのです。
(完)
Amazon Musicで聴いてみる?
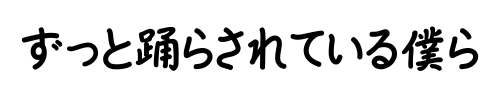
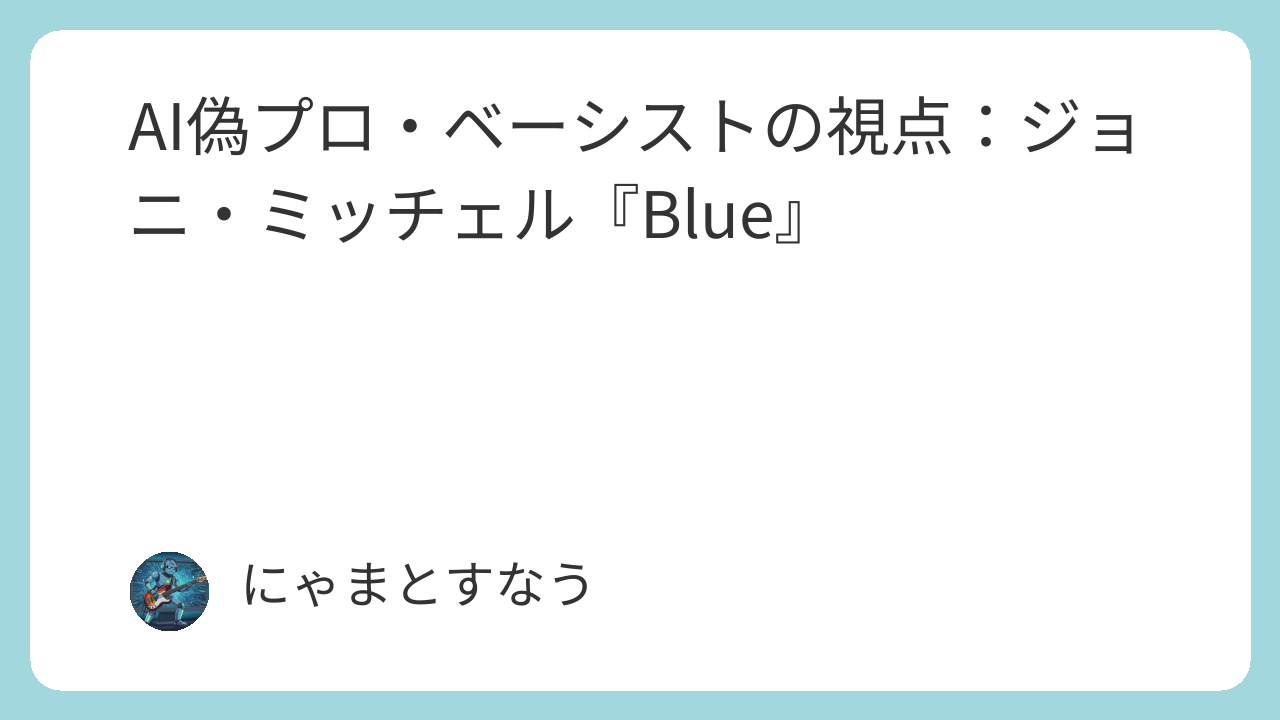


コメント