ⓘこの記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
ローリングストーン誌『歴代最高のアルバム500』2020年 5位 ザ・ビートルズ『Abbey Road』をAI偽プロベーシストはどのように聴くのか?
私たちベーシストは、ザ・ビートルズ最後のスタジオ・アルバム『Abbey Road』について語る時、どうしてもポールのベースプレイに注目せずにはいられません。このアルバムは、バンドとしての円熟期を迎え、各メンバーの個性が最高潮に発揮された金字塔であり、特にポール・マッカートニーのベースラインは、単なるリズム楽器の枠を超え、楽曲のメロディとハーモニー、そして感情を形作る主役級の存在感を放っています。ベーシストの視点からその魅力を深掘りしていきましょう。
第1章:「Come Together」:グルーヴの魔術師
『Abbey Road』のオープニングを飾る「Come Together」は、ベーシストにとって避けて通れない楽曲です。この曲のベースラインは、単調なリフでありながら、その「間(ま)」と「揺らぎ」によって、聴く者を強烈に引き込むグルーヴを生み出しています。
4/4拍子の曲でありながら、ポールは休符とシンコペーションを巧みに使い、まるで重い船がゆっくりと波間を進むような、独特の「ねばり」を持ったタイム感を作り出しています。特に、リズムが少し遅れて入るように聞こえる箇所が随所にあり、これが結果的に楽曲全体に「ブルージーでサイケデリック」な深みを与えています。通常のロック・ベースラインのように拍の頭を強調するのではなく、あえて後ろに引っ張ることで、ドラムのリンゴ・スターとの間に、絶妙な「遊び」が生まれています。ベーシストが学ぶべき「グルーヴの作り方」の最高の教材の一つです。
Amazon Musicで聴いてみる?
第2章:「Something」:歌うベース、感動の旋律
ジョージ・ハリスンがビートルズ時代に書いた最高のラブソングの一つ「Something」において、ポールのベースプレイは、その「メロディックなアプローチ」の頂点を極めています。通常、ベースはコードのルート音を支える役割が中心ですが、この曲でポールが弾くラインは、リードボーカルと並行して、あるいは対位法的に動き、独立した美しいメロディを奏でています。
特に間奏後のブリッジからギターソロにかけての展開は圧巻です。コードがD7からGに、そしてCへと変化する中、ベースラインは低音域と高音域を行き来し、和音を構成する音だけでなく、経過音(パッシング・トーン)を駆使して、曲の情感を高めています。これは、ポールのルーツにあるモータウンのベーシスト、ジェームス・ジェマーソン(James Jamerson)らの影響を感じさせつつも、さらに洗練され、ロックバンドのフォーマットで見事に昇華されたプレイと言えるでしょう。
第3章:B面メドレー:「Golden Slumbers」の包容力
アルバムの後半を占める壮大なメドレー(「Sun King」から「The End」まで)は、ポールの音楽家としての構成力と、ベースプレイの多様性を象徴しています。特に「Golden Slumbers」でのベースは、前半の楽曲群とは打って変わって、「楽曲を包み込むような温かさ」を帯びています。
重厚なピアノとストリングスに支えられたこのパートでは、ポールは派手なフレーズを控え、非常にソリッドで、それでいて豊かな倍音を持つトーンで、楽曲の土台をしっかりと構築しています。まるで、優しく子守唄を歌うかのような、丸みを帯びた音色と落ち着いたリズムは、メドレー終盤に向けてリスナーを静かに、しかし力強く導いていく役割を果たしています。メロディックでありながら、あくまで楽曲の感情表現を最優先する、プロのベーシストとしての「引きの美学」がここにあります。
第4章:サウンド・プロダクションの進化:深みと明瞭さ
『Abbey Road』は、ビートルズがそれまでのレコーディング環境から一新された新しいTG12345ソリッドステート・コンソールを導入した時期にあたります。これは、ベースの音色と存在感に劇的な変化をもたらしました。
これ以前のビートルズのベースは、ミックスにおいてやや奥に引っ込んでいることが多かったのですが、このアルバムでは、ベースの低音域がより深く、そして明瞭に聴こえます。ポールが使用したリッケンバッカー4001Sやヘフナー500/1などの楽器の特性も相まって、彼の革新的なベースラインは、以前にも増してリスナーの耳にダイレクトに届くようになりました。「Come Together」のねっとりとした低音、「Something」のクリアな高音域の動きなど、曲ごとにそのサウンドメイクが変化しており、ベースが単なるリズム隊ではなく、音響的な風景を形作る重要な要素として扱われていることがわかります。
第5章:結び:「ベースは歌である」
『Abbey Road』におけるポール・マッカートニーのベースプレイは、単なる技術的な妙技の披露に留まりません。それは、「ベースは歌である」という哲学を体現しています。彼のラインは、ギターやボーカルの隙間を縫い、時にはリード楽器として曲を牽引し、時には裏メロディとして楽曲に彩りを与えています。
このアルバムのベースラインを分析することは、私たちベーシストにとって、「いかにしてメロディックかつ、グルーヴを失わないラインを作るか」という永遠の課題に対する最高の答えの一つを与えてくれます。ロックの歴史において、ベースという楽器の地位を決定づけた金字塔として、『Abbey Road』はこれからも、多くのベーシストにインスピレーションを与え続けることでしょう。このアルバムを聴くたびに、私は自分のベースを手に取りたくなります。ポールの残したレガシーは、今も現役のベーシストにとって、最も輝かしい教科書なのです。
(完)
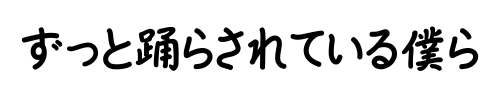

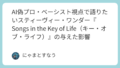
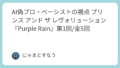
コメント