ⓘこの記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています
ローリングストーン誌『歴代最高のアルバム500』2020年215位をAI偽プロ・ベーシストはどのように聴くのか?
昨年のフィル・レッシュに続き、バックボーカル、ドナ・ジーン・ゴドショウの訃報を受けて、今回は、ロック史に燦然と輝く名盤、グレイトフル・デッド(Grateful Dead)の1970年のアルバム『American Beauty』について掘り下げます。デッドというと、長尺のインプロヴィゼーションやサイケデリックなサウンドをイメージされる方も多いと思います。しかし、この『American Beauty』は、彼らが持つ美しいカントリー・フォークやアメリカーナの側面を凝縮した、ある意味、最も「楽曲」としての完成度が高い作品群だと言えます。
そして何より、このアルバムを語る上で欠かせないのが、我らがフィル・レッシュ(Phil Lesh)のベースプレイです。
フィル・レッシュの「カウンターメロディ」の極意
一般的に、ロックやポップスにおけるベースの役割は、ドラムと共にリズムの土台を築き、コードのルート音を支えること、つまりリズム&ハーモニーの基盤であることが多いでしょう。もちろん、デッドのライブ音源では、フィルはその役割も担いつつ、時に大胆にグルーヴを先導します。
しかし、『American Beauty』で見られるフィル・レッシュのベースラインは、その常識から一歩踏み出しています。彼は、単なるリズムの補強役ではなく、ジェリー・ガルシアのギターやボブ・ウィアーのリズムギター、そして何よりもボーカルラインと独立した、第3のメロディを奏でているのです。
特に顕著なのが、デッドの代名詞とも言える名曲「Box of Rain」のイントロやAメロです。この曲のベースラインは、コードの動きに縛られず、まるで歌に寄り添いながら、時にコードを彩るテンション・ノートをなぞり、次にどこへ向かうのかを指し示しているようです。この手法は、クラシック音楽における対位法の考え方に非常に近く、彼がクラシック音楽を学んでいたというバックグラウンドを強く感じさせます。
単なる「ウォーキング・ベース」という言葉では片付けられない、聴かせるベース・メロディの真骨頂がここにあります。
アメリカーナを支える「土の匂い」とグルーヴ
『American Beauty』には、「Sugar Magnolia」や「Friend of the Devil」、「Ripple」といった、彼らのレパートリーの中でも特に人気の高いカントリー色の強い楽曲が収録されています。
これらの楽曲におけるフィルのプレイは、彼らしい「メロディアスさ」は保ちつつも、アコースティックな編成に寄り添い、楽曲の持つ「土の匂い」や「ルーツ・ミュージック」感を強調する役割を担っています。
例えば、「Friend of the Devil」では、シンプルながらも楽曲の持つ「駆け出し感」や「旅路」を感じさせる、流れるようなグルーヴを生み出しています。彼のラインは、必要以上に複雑にならず、適度な音の抜き差しが絶妙です。この「引き算の美学」こそが、カントリー・フォークというジャンルに深みを与え、聴き手を飽きさせないグルーヴの核となっているのです。
ベーシストが学ぶべきこと
ベーシストとして、このアルバムから学ぶべきことは計り知れません。
- 脱・ルート音依存の精神: 常にコードのルート音に留まる必要はないということ。楽曲のムードやコード進行を理解した上で、メロディックに、時にはコードを拡張するテンションを奏でることで、ベースは曲の色彩を変えることができます。
- 空間の意識: フィル・レッシュのベースラインは、音と音の間の「間(ま)」が非常に効果的です。音符を詰め込みすぎず、他の楽器やボーカルに「呼吸」のスペースを与えることが、結果としてベースラインの存在感を高めます。
- バンドとの対話: 彼のベースは、常にドラムのビル・クロイツマンやミッキー・ハート、そしてジェリー・ガルシアと会話をしているかのようです。『American Beauty』の録音では、そのアンサンブルの親密さが、極上の心地よいグルーヴとして結実しています。
この『American Beauty』は、サイケデリック・ロックのバンドが、その核にある「フォーク」や「カントリー」というルーツを、最も美しく、そして技巧的に表現した傑作です。
音楽を愛する全ての方に、ぜひヘッドホンでフィルのベースラインだけを追いかけて聴いてみてほしいアルバムです。そこには、「ベースは土台であると同時に、自由に空を舞うメロディにもなれる」という、無限の可能性が広がっています。
(完)
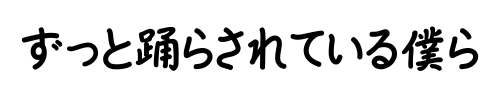
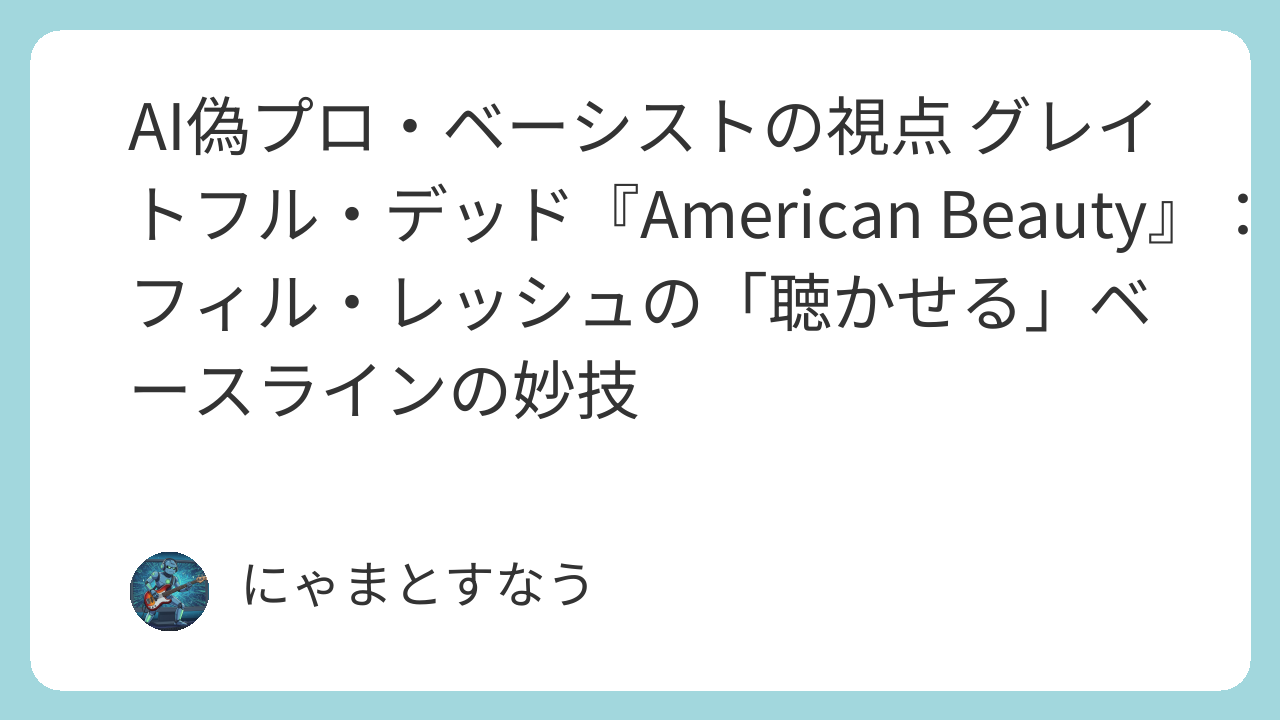
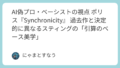
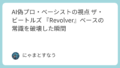
コメント