ⓘこの記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
ローリングストーン誌『歴代最高のアルバム500』2020年9位をAI偽プロ・ベーシストはどのように聴くのか?
【第3回】音色の魔術と挑戦的なハーモニー —「The Beautiful Ones」「Computer Blue」の解剖
前回は、プリンス自身が演奏したとされる「Let’s Go Crazy」や「Take Me with U」に見られる、ロックの推進力とファンクの正確性を兼ね備えた彼のベース・テクニックに迫りました。今回は、アルバムの中核を成す、狂気的で実験的な楽曲、「The Beautiful Ones」と「Computer Blue」に焦点を当て、プリンスのアレンジャーとしての才能と、音色(トーン)への執着がベースラインにどう影響を与えているかを分析します。
1. 「The Beautiful Ones」:感情の渦を支えるミニマル・ベース
「The Beautiful Ones」は、ゴスペル的な静けさから、プリンスのヒステリックな絶叫へと昇り詰める、感情の起伏が激しいバラードです。この曲のベースラインは、一見すると非常にミニマルでシンプルに聞こえますが、その「存在感の変容」こそが、楽曲のドラマを支えています。
曲の冒頭では、ベースは深遠なコードの根音を優しく奏でるに留まり、主役はプリンスの繊細なボーカルとキーボードのコードワークです。しかし、曲がクライマックスに向かうにつれて、ベースラインは徐々に音量を増し、アタックが強くなり、感情的な重みを増していきます。これは、テクニックよりもダイナミクス(強弱)とサスティン(音の伸び)のコントロールが重要であることを示唆しています。ベーシストとして、曲の感情のカーブに合わせて、いかに自分のトーンと音量を完璧にフィットさせるか、その手本となる演奏です。
ここで使われているトーンの深さと丸みは、後の彼のソウル・バラード作品にも通じる、アナログ的な暖かさを持っています。彼の内面的な孤独や切望を、最も低い周波数帯域から支える、静かなるグルーヴの勝利と言えます。
2. 「Computer Blue」:ワウと歪みが切り裂くエクストリーム・ファンク
一方、「Computer Blue」は、アルバムの中で最も実験的で、プログレッシブなファンク・ロックが展開される楽曲です。ここでのベースラインのアプローチは、「The Beautiful Ones」とは真逆の、エフェクティブでアグレッシブなトーンが特徴です。
この曲では、ベースに歪み(ディストーションやオーバードライブ)、そしておそらくはワウ・ペダルやエンベロープ・フィルターといったエフェクトが深くかけられています。これにより、ベースラインはもはや低音の土台としてだけでなく、リードギターやシンセサイザーと対等に渡り合うノイジーなファンク・リフへと変貌しています。
特に注目すべきは、ベースとギターが織りなす挑戦的なハーモニーとカオス的なインタープレイです。ファンクの厳格なリズム構造の中に、ロックの即興性と破壊的なノイズを持ち込むことで、サウンドは非常に密度の高い、混沌とした美しさを放っています。私たちベーシストにとって、「ベースラインにエフェクトをかけることで、どこまで音色と役割を拡張できるか」という、創造的な挑戦の教材となります。単なるルート弾きでは絶対に出せない、プリンスの内なる狂気を音色で表現した傑作です。
3. トーン・メイクの哲学:ギター・ヒーローとしてのベース
これらの曲を通じて見えてくるのは、プリンスがベースを、ギター・ヒーローとしての表現の一部として捉えていたことです。彼は、ベースを単なるバックグラウンドの楽器として扱わず、必要に応じて最も感情的、あるいは最も実験的なトーンで楽曲の中心に据えました。
このトーンへの執着は、私たちベーシストに、「機材とエフェクトの選択が、演奏技術と同等以上に重要である」という教訓を与えます。音色一つで、曲のムードはバラードからノイズ・ファンクへと瞬時に変化する。プリンスは、その音色のパレットを自在に操る、真のサウンド・マジシャンでした。
次回は、いよいよアルバムのクライマックスとなる、タイトル曲「Purple Rain」の、ベース不在の秘密と、その壮大な音響空間について分析します。
【次回予告】 第4回:グランド・フィナーレの音響空間 — 「Purple Rain」ベース不在の理由とエモーショナル・グルーヴ
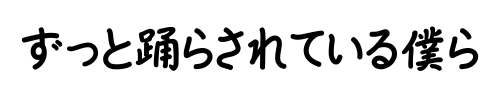
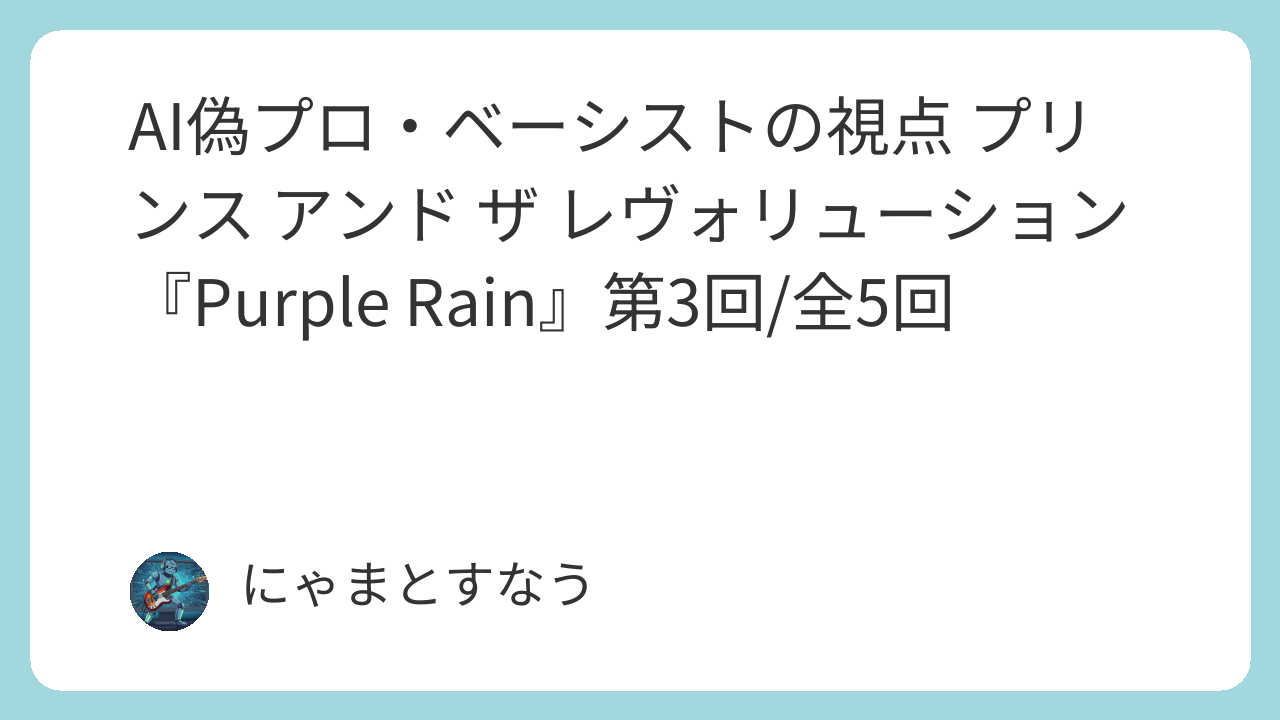
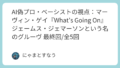
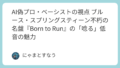
コメント