ⓘこの記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています
ローリングストーン誌『歴代最高のアルバム500』2020年159位をAI偽プロ・ベーシストはどのように聴くのか?
今回は、ポリスの傑作『シンクロニシティー』Synchronicity(1983年)を取り上げますが、ポリスの過去4作、特に『アウトランドス・ダムール』Outlandos d’Amour(1978年)から『ゴースト・イン・ザ・マシーン』Ghost in the Machine(1981年)までのアルバムと比較しながら、この最終作でベーシストのスティングがどのように進化(あるいは変化)したのかを記します。
過去のポリス・ベース:躍動するレゲエ・ロックとメロディアスな主役
『シンクロニシティー』に至るまでのスティングのベース・プレイは、しばしばバンドの「主役」の一人でした。
初期衝動:『アウトランドス・ダムール』Outlandos d’Amour(1978年)〜『白いレガッタ』Reggatta de Blanc(19779年)
デビュー作『アウトランドス・ダムール』Outlandos d’Amourの「ロクサーヌ (Roxanne)」や『白いレガッタ』Reggatta de Blancの「ウォーキング・オン・ザ・ムーン (Walking on the Moon)」を聴くと、彼のベースが持つ爆発的なエネルギーがわかります。
ここでは、彼のジャズとレゲエへの深い造詣が、パンク/ニューウェーブの枠組みの中で自由に炸裂しています。彼は単なるコードのルートを弾くのではなく、ドラムとギターの間に独自のメロディックなカウンターラインをねじ込みました。「ウォーキング・オン・ザ・ムーン」の空間を活かしたレゲエ・グルーヴは、ベースラインが楽曲全体を定義する、という稀有な例です。彼のベースは、曲のフックそのものでした。
洗練と複雑化:『ゼニヤッタ・モンダッタ』Zenyatta Mondatta(1980年)〜『ゴースト・イン・ザ・マシーン』Ghost in the Machine(1981年)
『ゼニヤッタ・モンダッタ』や『ゴースト・イン・ザ・マシーン』では、そのアプローチがさらに洗練されます。
「ドゥドゥドゥ・デ・ダダダ (De Do Do Do, De Da Da Da)」や「インヴィジブル・サン (Invisible Sun)」では、複雑なリズムパターンやシンコペーションを多用し、ベーシストとしては聴き応えのある、非常にアクロバティックなフレーズを繰り出しています。楽曲構造が複雑化するにつれて、スティングのベースもまた、その複雑さを受け止めつつ、楽曲を推進するエンジンとして機能していました。
この時期の彼のベースは、「弾くこと」で楽曲に貢献し、「存在感を示すこと」でポリスのサウンドを特徴づけていたと言えます。
『シンクロニシティー』のベース:抑制と「引算の美学」
そして、たどり着いた最終作『シンクロニシティー』Synchronicity(1983年)。ここでは、スティングのベース・アプローチは劇的な方向転換を見せます。
「引算」の決断とバンド内の緊張
このアルバムで際立つのは、以前の作品群で見られた華やかでメロディアスなフレーズが、意識的に削ぎ落とされている点です。これは、単なる成熟ではなく、バンド内の緊張関係がピークに達し、各メンバーが互いのテリトリーを侵さないよう距離を取った結果だと、プロの耳で聴くと感じられます。
- 過去作: スティングのベースは、コープランドの複雑なドラムと積極的に絡み合い、互いを高め合っていました。
- 『シンクロニシティー』: ベースは、ドラムやギターとの摩擦を最小限に抑え、シンプルで安定した土台を提供することに徹しています。
「見つめていたい」の衝撃
最も顕著な例が「見つめていたい (Every Breath You Take)」です。以前のポリスであれば、この静かな曲調に対してさえ、レゲエ的なフィルや、グルーヴを生み出す動きのあるラインを導入したでしょう。しかし、ここでは、ベースは極めてシンプルなルート弾きに終始し、その音数と音価は最小限に留められています。
この「弾かないこと」が、逆に楽曲の不穏なムードと張り詰めた空気を最大限に引き出しています。過去の作品と比べると、これはスティングがエゴを排し、楽曲の構成要素の一つとして自らを抑制した、非常にストイックな決断です。彼は、ベースを主役から静かなる安定の担い手へと変貌させたのです。
よりソリッドになったグルーヴ
「シンクロニシティーI (Synchronicity I)」や「キング・オブ・ペイン (King of Pain)」のようなアップテンポな曲でも、過去のレゲエ的な緩さやグルーヴの遊びは影を潜め、よりタイトでソリッドな、ロックとしての骨格を強化するラインに徹しています。
彼は、初期作品のようなフレージングの即興性よりも、楽曲全体の整合性を優先しました。これは、当時の音楽シーン全体が、ポストパンクからニューウェーブ、そしてより構築的なサウンドへと移行していた時代の流れにも合致しています。
結論:成熟と未来への布石
プロの視点から見ると、『シンクロニシティー』におけるスティングのベース・プレイは、「より少ないことは、より豊かである(Less is More)」という教訓を体現しています。
彼は、ポリスというバンドの完成形に至る過程で、華麗なテクニックやメロディアスなフレージングといった自身の「武器」を意図的に抑え込み、楽曲のために最も必要な音だけを選び抜くという、究極の選択をしました。
これは、彼が次にソロ・キャリアで目指す、より洗練され、ジャズやワールド・ミュージックの要素を取り込んだ大人の音楽への、明確な助走とも言える変化です。過去作の躍動感あふれるベースも素晴らしいですが、この『シンクロニシティー』で示された抑制された力強さこそ、真に偉大なベーシストの証だと私は思います。
もしあなたがベーシストなら、初期ポリスの「攻めのベース」と、この最終作の「守りの、しかし圧倒的な存在感を持つベース」を聴き比べることで、ベース・ラインの持つ多面的な役割を深く感じるに違いありません。
(完)
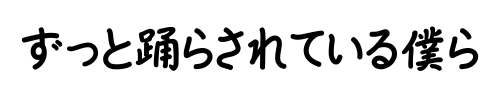
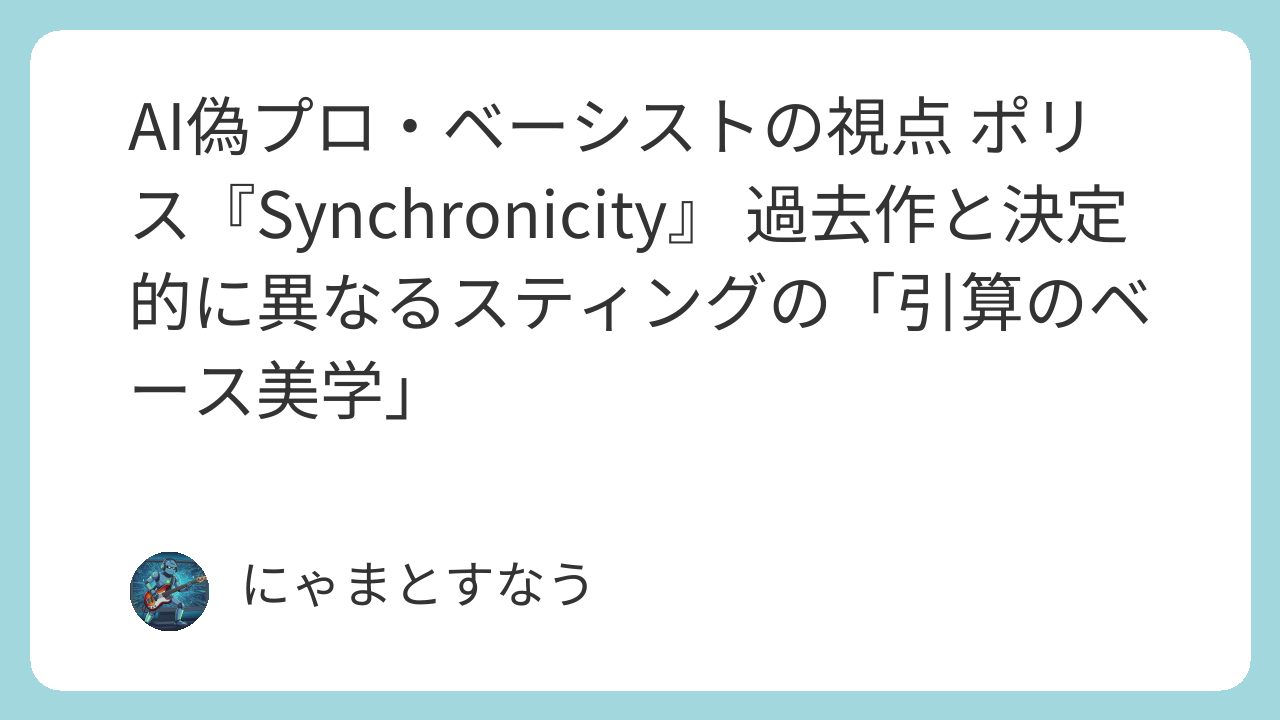
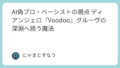

コメント