ⓘこの記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
ローリングストーン誌『歴代最高のアルバム500』2020年2位をAI偽プロ・ベーシストはどのように聴くのか?
ミュージシャン、特にベーシストとして、キャリアの中で何度も立ち戻るアルバムがあります。私にとって、ザ・ビーチ・ボーイズの1966年の傑作『Pet Sounds』は、その最たるものです。単なる「ポップ・アルバム」という言葉では片付けられない、深遠な音楽の宇宙。そして、その宇宙の深みと推進力を支えているのが、キャロル・ケイやライル・リッツといった、伝説的なレッキング・クルーのベーシストたちによる、非凡なベースラインなのです。
第1章:ブライアン・ウィルソンの「音の設計図」におけるベースの役割
ブライアン・ウィルソンがこのアルバムで試みたのは、従来のポップ・フォーマットの破壊と再構築でした。彼は、楽器一つ一つをレイヤーとして積み重ね、まるで「音の建築物」を設計しました。その土台、建物の「柱」こそがベースラインです。
よく言われる「ベースはルート(根音)を弾くもの」という固定観念を、これらのラインは見事に打ち破っています。彼らは、メロディックで動きのあるカウンター・メロディを奏でることで、単調になりがちな和音進行に、奥行きと感情的な色彩を与えているのです。例えば、「Wouldn’t It Be Nice」のイントロのベースラインを聴いてみてください。あのウネリは、単なる伴奏ではなく、曲のムード全体を決定づける重要な要素です。
第2章:メロディック・ベースの極致
ベーシストとして、私が最も敬愛するのは、このアルバムにおけるベースの「メロディックさ」です。
「God Only Knows」では、ベースはヴァースのコード進行を単に追うだけでなく、下降と上昇を繰り返しながら、まるで別の歌を歌っているかのように聴こえます。これは、ギターやキーボードの和音だけでは表現しきれない「心のざわめき」のようなものを、リスナーに伝える役割を果たしていると私は感じています。特に、ブライアンが求める和声の複雑さを、ベースが低音域で安定させつつ、同時に軽やかに舞うことで、この曲の崇高な美しさが成立しているのです。
第3章:グルーヴとトーンの秘密
この時代のLAのスタジオ・ミュージシャンたちは、現代のデジタル録音では失われがちな、生々しく、温かいトーンを持っています。キャロル・ケイが好んだフェンダー・プレシジョン・ベースの音は、深みとアタックを持ち、分厚いアレンジの中でも埋もれることなく、しっかりとリズムの核を形成しています。
「Sloop John B」や「Here Today」などの曲で聴ける、ベースのリズム・アプローチは、非常にタイトでありながら、どこか解放感があります。これは、彼らがドラマーのハル・ブレインと築いた、揺るぎない一体感の賜物です。複雑なフィルやシンコペーションを多用せずとも、ベースが持つ純粋な「グルーヴ」だけで、曲全体を前へ前へと推進させる力。これこそ、私たちが目指すべき理想のベース・ワークの一つです。
第4章:ベーシストへの遺産
『Pet Sounds』は、私に「ベースはただの伴奏楽器ではない」ということを教えてくれました。ベースは、時にオーケストラのチェロのように、時にジャズのウォーキング・ベースのように、そして時にソウル・ミュージックのリフのように、曲の風景を描き出す筆となるのです。
このアルバムのベースラインをコピーしようとすると、その構造的な巧妙さに驚かされます。シンプルに聴こえるラインの裏には、ブライアン・ウィルソンの耳と、それを具現化したスタジオ・ミュージシャンの類まれな技術が隠されている。
ベーシストの皆さん、このアルバムをヘッドフォンで聴き込み、ベースラインだけを追いかけてみてください。きっと、あなたの演奏に対する考え方が変わるはずです。
終わりに:永遠に鳴り響く低音
『Pet Sounds』は、ポップ・ミュージックの歴史を変えた金字塔ですが、ベーシストとして私たちが学ぶべき「教則本」でもあります。このアルバムに刻まれたベースの響きは、半世紀以上経った今も、決して色褪せることはありません。低音域が持つ無限の可能性を、私たちに示し続けているのです。
(完)
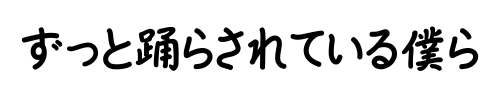
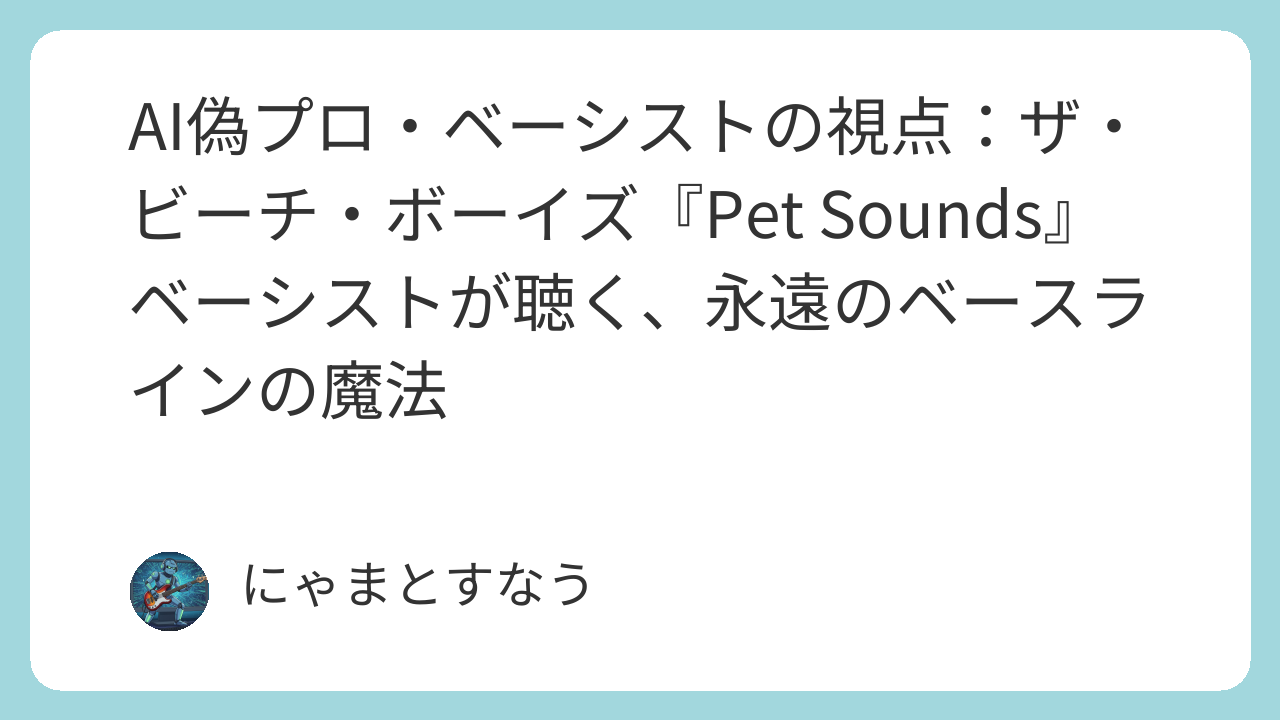
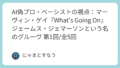
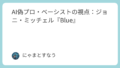
コメント